労災保険の「特別加入」とは。一人親方の「もしも」の備えを徹底解説

労働者を使用する事業主は、労災保険への加入が法律で義務付けられています。しかし一人親方のように労働者を使用せずに独立して働く自営業者は、原則としてこの労災保険の対象外となります。
そのため、一人親方が怪我や病気で働けなくなった場合のセーフティネットとして設けられたのが「特別加入制度」です。
この記事では、特別加入制度の概要や必要性、手続き方法について、特に建設業の一人親方に焦点を当てて解説します。
労災保険の特別加入制度について
ここからは、一人親方労災保険の特別加入制度の全体像について説明していきます。
特別加入とは
特別加入とは、本来は労災保険の対象とならない自営業者や中小事業主などが、特例として労災保険に任意加入できる制度です。
この制度によって、労働者と同様に労災保険の補償を受けることが可能になります。労災保険は、業務上の怪我や病気、もしくは通勤中の事故などに対し補償を提供する公的な保険制度です。
特別加入の3つの区分
特別加入制度は大きく分けて3つの区分があります。
| 区分 | 対象者 | 概要 |
|---|---|---|
| 第1種特別加入 | 中小事業主等 | 中小企業の事業主や役員など、労働者ではないが事業に従事する方を対象とした区分 |
| 第2種特別加入 | 一人親方等 | 建設業などの一人親方、個人タクシー、漁船自営業者など労働者を使用せず事業を行う方を対象とした区分 |
| 第3種特別加入 | 特定作業従事者 | 海外派遣者、特定の危険有害業務従事者など、特定の環境で働く方を対象とした区分 |
第1種特別加入は中小事業主等、第2種特別加入は一人親方等、第3種特別加入は特定作業従事者(海外派遣者など)を対象としています。この記事では、建設業の一人親方が対象となる第2種特別加入について詳しく解説します。
特別加入については以下で詳細が記載されています。当団体でご確認ください。
当団体では比較的安価な料金設定、クレジットカード決済対応、優待や特典など充実のサービスで一人親方の労災保険加入をサポートしています。
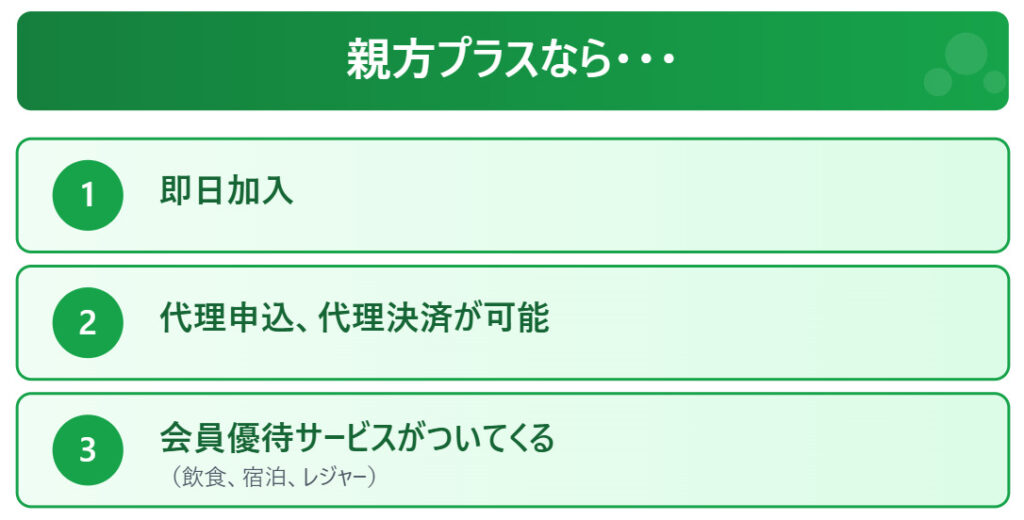
親方プラスなら・・・
- 即日加入
- 代理申込、代理決済が可能
- 会員優待サービスがついてくる(飲食、宿泊、レジャー)
労災保険の特別加入が一人親方にとってなぜ大切なのか
続いて、一人親方にとっての労災保険の重要性について解説します。特別加入に入ることはなぜ必要なのでしょうか。
労災に見舞われる可能性
一人親方、特に建設業などでは、高所作業や重機の操作など危険を伴う作業に日常的に従事しています。厚生労働省の統計によると、建設業における労働災害の発生率は全産業平均の約2倍にもなります。実際、2023年の建設業における労働災害による死亡者数は約223人、休業4日以上の死傷者数は約14万人近くにのぼり、その中には多くの一人親方も含まれています。(参照:厚生労働省)
発生するリスク
特別加入していない場合、業務中の怪我や病気は健康保険の対象となりますが、様々な面で不利になります。例として以下をご確認ください。
| 項目 | 特別加入なし(健康保険適用) | 特別加入あり(労災保険適用) |
|---|---|---|
| 治療費 | 3割自己負担 | 全額補償 |
| 休業補償 | なし | 給付基礎日額の60%〜80% |
| 後遺障害補償 | 限定的 | 障害等級に応じた補償 |
| 通勤災害 | 対象外の場合あり | 対象 |
特別加入していれば、治療費は全額補償され、休業期間中も給付基礎日額の60%〜80%の補償を受けられます。後遺障害が残った場合も、その程度に応じた補償を受けることができ、通勤災害も補償の対象となります。
家族なども安心
特別加入制度は、公的保障制度から漏れやすい立場にある一人親方にとって、重要なセーフティネットです。事故や疾病によって働けなくなった際に、本人だけでなく家族の生活を守るうえでも、大きな役割を果たします。実際に、特別加入制度を利用して適切な補償を受けられた一人親方の事例は数多く報告されています。
当団体では比較的安価な料金設定、クレジットカード決済対応、優待や特典など充実のサービスで一人親方の労災保険加入をサポートしています。
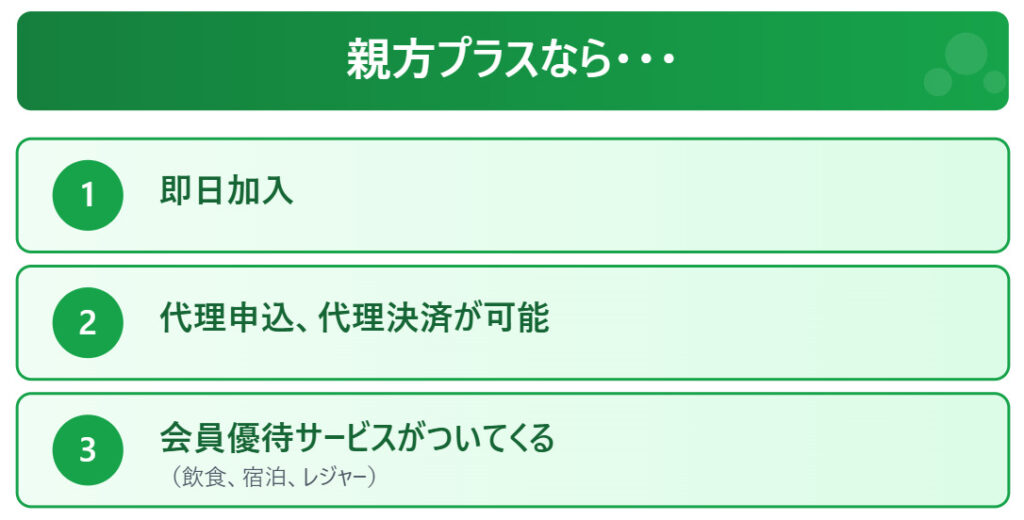
親方プラスなら・・・
- 即日加入
- 代理申込、代理決済が可能
- 会員優待サービスがついてくる(飲食、宿泊、レジャー)
特別加入の対象と条件
ここからは労災保険の特別加入の対象となる、一人親方の職種を見ていきましょう。
対象となる職種と業種
建設業では大工、左官、とび、石工、解体工、建設機械操作者などが特別加入の対象に該当します。建設業以外にも、個人タクシーや個人貨物運送業者、漁船による自営漁業者、林業従事者、廃棄物処理業者なども対象となっています。職種の範囲は広いですが、自身の仕事が対象となり得るか事前の確認を怠らないようにしましょう。
加入条件
特別加入の条件として最も重要なのは「労働者を使用していないこと」です。アルバイトやパートタイマーであっても定期的に雇用している場合は、特別加入ではなく事業主として通常の労災保険に加入する必要があります。また、請負契約または業務委託契約に基づいて仕事をしていることも条件となります。
労災保険の補償内容
次に一人親方が労災保険に加入した際の主な補償内容は以下となります。
| 給付の種類 | 内容 | 支給条件 |
|---|---|---|
| 療養補償給付 | 治療費の全額補償 | 業務上の負傷・疾病 |
| 休業補償給付 | 給付基礎日額の60%+特別支給金20% | 療養のため労働不能な期間(4日目から) |
| 障害補償給付 | 障害等級に応じた一時金または年金 | 治療後に障害が残った場合 |
| 遺族補償給付 | 遺族に対する一時金または年金 | 業務上の事由による死亡 |
| 介護補償給付 | 介護費用の補償 | 重度障害で常時介護が必要な場合 |
特別加入制度は、公的保障から漏れやすい立場にある一人親方にとって、重要なセーフティネットです。事故や疾病によって働けなくなった際に、本人だけでなく家族の生活を守るうえでも、大きな役割を果たします。
当団体では比較的安価な料金設定、クレジットカード決済対応、優待や特典など充実のサービスで一人親方の労災保険加入をサポートしています。
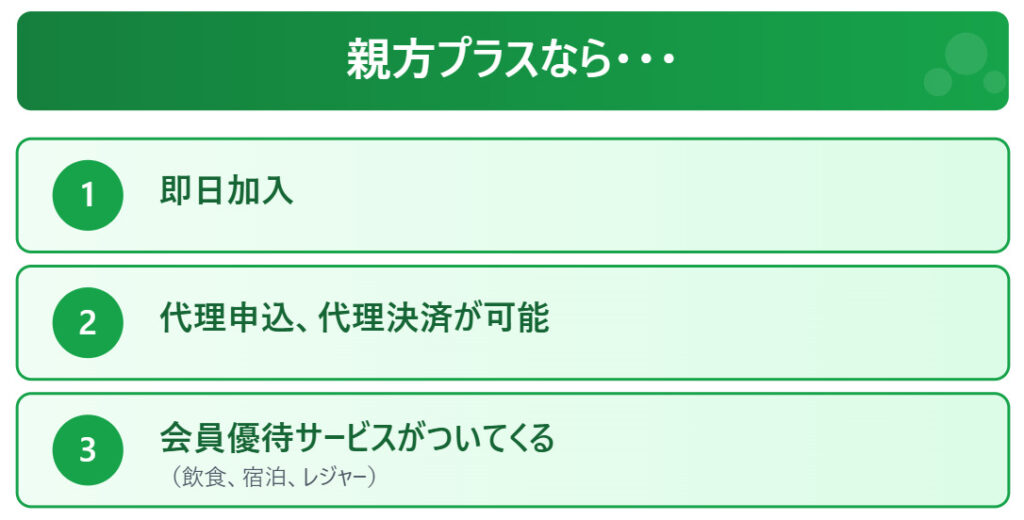
親方プラスなら・・・
- 即日加入
- 代理申込、代理決済が可能
- 会員優待サービスがついてくる(飲食、宿泊、レジャー)
特別加入の保険料
保険料の計算方法
特別加入の保険料は「給付基礎日額 × 365日 × 保険料率」で計算されます。例えば、給付基礎日額10,000円、保険料率1.7%(建設業の一人親方の場合)であれば、10,000円 × 365日 × 0.017 = 62,050円が年間保険料となります。
月額に換算すると約5,170円となり、民間の傷害保険と比較して割安な保険料で補償を受けられるのが特徴です。
業種別保険料率
以下は、2024年4月1日以降に適用されている最新の特別加入保険料率(第2種)です。主な業種を記載します。
| 分野・業種 | 保険料率(2024年4月以降) |
|---|---|
| 建設業の一人親方 | 17/1,000 |
| 個人タクシー・貨物運送業者 | 11/1,000 |
| 自営漁業者(漁船による) | 45/1,000 |
| 林業の一人親方 | 52/1,000 |
| 医薬品の配置販売業者 | 6/1,000 |
※これらの料率は厚生労働省が毎年度見直しを行っており、将来的に変更される可能性もあります。最新情報は厚生労働省の公式Webサイト等でご確認ください。
2025年4月現在の特別加入の保険料率は、業種によって大きく異なります。建設業の一人親方は17/1,000(1.7%)、個人タクシー等は11/1,000(1.1%)、自営漁業者は45/1,000(4.5%)、林業の一人親方は52/1,000(5.2%)、医薬品配置販売業者は6/1,000(0.6%)となっています。
これらの保険料率は、各業種の労災リスクの高さを反映したものです。
注意!保険料は経費計上できない
労災保険料はあくまでも「個人」のためのものであり、一人親方の業務そのものとは切り離されて考えられます。
そのため「経費計上」はできません。事業経費としてはみなされないので注意が必要です。
ちなみに、労災保険の手続きでかかる事務手数料、後述する団体に支払う会費等は経費になります。経理の際には、しっかりと勘定科目を分けるようにしましょう。
経費に関しての詳細は以下の記事をご覧ください。
→ 労災保険は経費になる?
特別加入団体に加入する
特別加入するには「特別加入団体」へ加入する必要があります。これは、労働局長の認可を受けた団体で、建設業では建設業労災保険組合や地域の一人親方組合が該当します。直接労働基準監督署に申請することはできませんので注意が必要です。
また、団体によって入会金や年会費、提出書類の内容が異なるため、事前に複数の団体を比較検討することをおすすめします。費用対効果や手続きのサポート体制なども考慮して選ぶとよいでしょう。
特別加入団体での更新や解約などは以下でも解説しています。
当団体では比較的安価な料金設定、クレジットカード決済対応、優待や特典など充実のサービスで一人親方の労災保険加入をサポートしています。
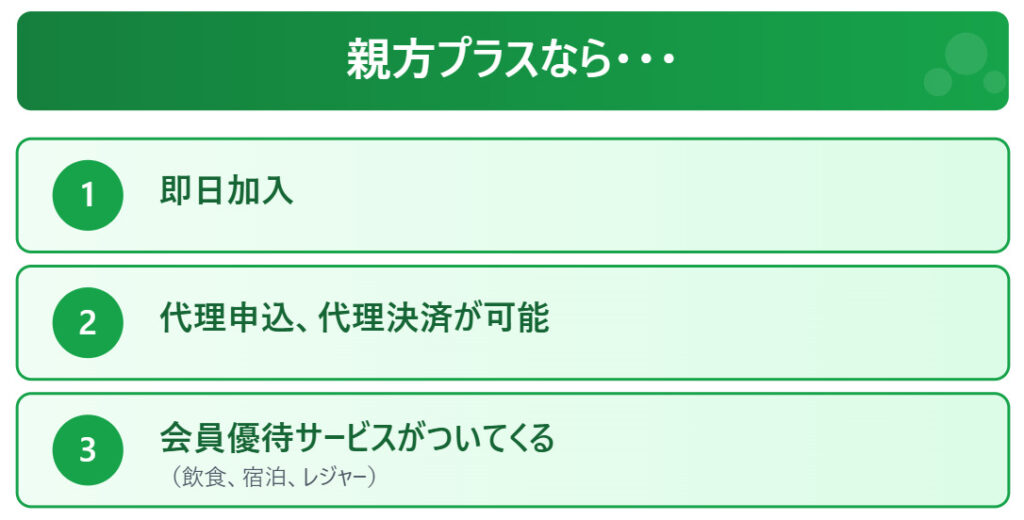
親方プラスなら・・・
- 即日加入
- 代理申込、代理決済が可能
- 会員優待サービスがついてくる(飲食、宿泊、レジャー)
加入に必要なものと手順
特別加入の申請には、主に以下の4種類の書類が必要です。
必要な書類
- 特別加入申請書:特別加入団体を通じて提出する基本的な申請書類
- 特別加入に関する証明書:特別加入団体が発行する証明書
- 業務内容の証明書類:請負契約書のコピー等
- 本人確認:運転免許証のコピー等
- 必要書類を揃えて団体に提出します。
書類以下の手順で加入を進めます。
加入手順
➡労災保険の申込み(公的身分証明書提出)
➡費用の決済・振込
➡団体は労基署および労働局へ電子申請で加入手続き
➡加入証明書発行および労働保険番号通知(最短翌日が保険適用日)
申請から承認までには通常2週間〜1ヶ月程度かかるため、余裕を持って準備しましょう。
加入方法については以下の記事でも詳しく解説しています。ご覧ください。
給付基礎日額の選択
加入申請時には「給付基礎日額」を選択します。これは保険料の算出基礎であると同時に、給付時の金額にも大きく関わる重要な項目です。現在は3,500円〜25,000円の範囲で選択可能です。
給付基礎日額を高く設定すればするほど、保険料も上がりますが、その分補償も手厚くなります。たとえば20,000円を選んだ場合、休業補償は1日あたり16,000円(80%)となり、月額約48万円の補償が受けられます。
実収入や生活費とのバランスを考慮して、無理のない範囲で最適な金額を選びましょう。あまり低く設定すると補償が不十分になる可能性があり、逆に高すぎると保険料負担が大きくなるため、自身の収入状況に合わせた適切な選択が重要です。
料金については以下の記事もチェックしてみてください。
特別加入で一人親方の安全を守る
特別加入制度は、一人親方が労災保険という公的保障を活用できる重要な制度です。建設業など危険の伴う業種に従事する方にとって、特別加入は自身と家族の生活を守るための欠かせないものとなります。
業務上の事故や疾病による治療費の全額補償、休業期間中の金銭の補償、障害が残った場合の補償など、特別加入の補償内容は充実しています。
加入手続きが複雑に感じられる場合でも、当団体・親方プラスなどのサポートサービスを活用すれば、スムーズに加入することができます。一人親方として独立して働く自由を選んだからこそ、その自由を守るため、労災保険には加入する方が無難です。
ご自身やご家族の安心のため、特別加入をお忘れなく。
投稿者プロフィール

- 代表理事
-
いつもコラムをお読みいただきありがとうございます。
『建設業界を元気にしたい!』そんな思いで建設業に従事する方々が抱える問題点や悩み事に少しでもお役に立てれば幸いです。
【略歴】
・2011年 某外資系保険会社に入社
・2013年 労災保険特別加入団体の運営を開始
・2016年 大手生命保険会社100%出資代理店へ転身
・2024年 一人親方労災保険連合会【親方プラス】を設立 現在に至る
【趣味・特技】
キャンプ、つり、スキー、サッカー、ゴルフ…etc
最新の投稿
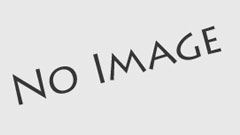 お知らせ2026年2月3日第2種特別加入労災保険の新年度更新時期となります
お知らせ2026年2月3日第2種特別加入労災保険の新年度更新時期となります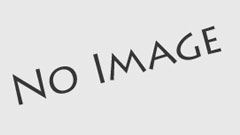 お知らせ2025年12月25日年末年始の休業日と新規ご加入についてのお知らせ
お知らせ2025年12月25日年末年始の休業日と新規ご加入についてのお知らせ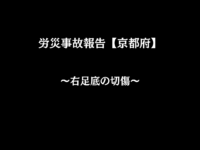 労災事例2025年9月25日【労災事故報告】令和7年8月7日 材料の運搬中に段差を踏み外し負傷したのも
労災事例2025年9月25日【労災事故報告】令和7年8月7日 材料の運搬中に段差を踏み外し負傷したのも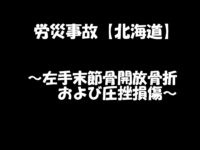 労災事例2025年8月25日【労災事故報告】令和7年8月11日 荷下ろし中にあおりに挟まれ末節骨開放骨折・圧挫損傷
労災事例2025年8月25日【労災事故報告】令和7年8月11日 荷下ろし中にあおりに挟まれ末節骨開放骨折・圧挫損傷

