一人親方とは?個人事業主との違いやメリット・デメリットについてわかりやすく解説

一人親方なのか?それとも個人事業主なのか?
自分の立場がよくわからないと思っている方や、一人親方だと思い込んで仕事に従事している方も多くいます。この記事では、一人親方と個人事業主の違いとそれぞれのメリット・デメリットまでわかりやすく解説します。これから独立を考えている方にもお役立ていただける内容です。理解を深め適正な処遇を受けていただくためにも最後まで読んでいただけると幸いです。
一人親方とは
一人親方とは、前提として会社(法人)や個人(事業主)から雇用されず、元請事業者から仕事を請負って(業務委託)単独で仕事をする方を言います。また、家族以外の他人従業員(アルバイト)は年間99日以上は使用せずに特定の業種に限ってのみ仕事をする方が一人親方です。※配偶者を専従者として雇うケースや子供と一緒に仕事をすることもあります。
一人親方は「職人」なのか
一人親方は所謂『職人』と言い換えれますが、その職人には下記の通り4つの職階級があります。
①見習工(従弟)→②職人(技能者)→③一人親方(独立自営業者)→④親方(経営者)
この階級からいくと一人親方は親方の下で見習工や職人を使用して仕事ができる最高位の独立した職人と称される位です。しかし、昨今の職人業界では「人を雇えなくなった」「雇ってくれるところがない」このような理由でやむなく一人親方になったというケースが多くなっています。
一人親方の仕事は事故・怪我リスク高
次の章を見れば明らかですが、一人親方の仕事は建設業を筆頭に現場作業が多く、だからこそ事故やケガのリスクが常に付きまとう仕事も少なくありません。
だからこそ一人親方には人一倍の安全意識が求められますが、どれだけ注意したとしても、リスクを0にすることはできません。
そんな一人親方にとって重要になるのが労災保険です。一人親方は労働者ではありませんが、仕事の性質が労働者に近い点もあり「特別加入」の形で労災保険に入ることができます。
特別加入は国の認可を得た「特別加入団体」に入ることが条件となります。当団体もそれに該当し、比較的安価な料金設定やクレジットカード決済、スピーディーな加入手続きなど充実のサービスで一人親方を支援しています。加入を検討する余地のある方は、必ずご確認ください。
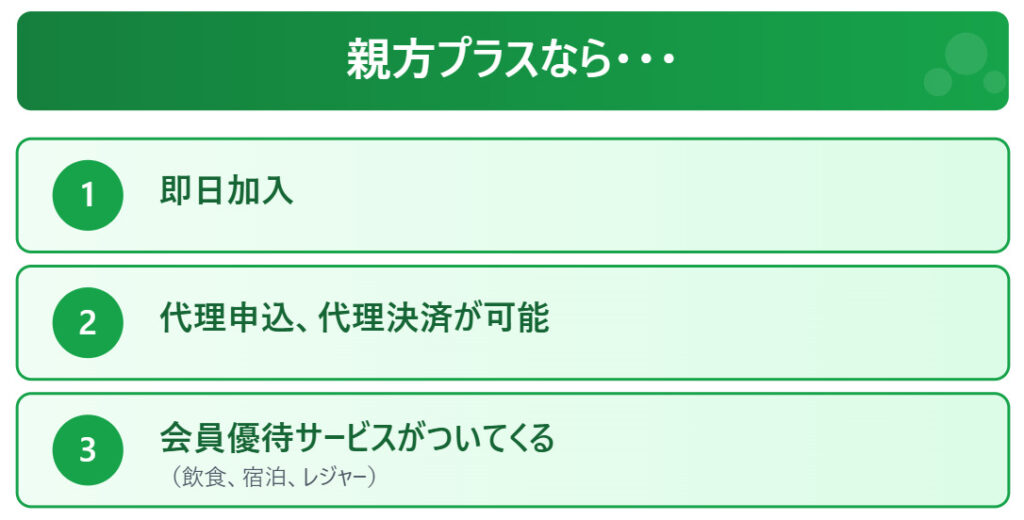
親方プラスなら・・・
- 即日加入
- 代理申込、代理決済が可能
- 会員優待サービスがついてくる(飲食、宿泊、レジャー)
一人親方労災保険については以下でも詳細を解説しています。ぜひご覧ください。
一人親方として認められる業種と職種
一人親方として従事できる仕事は、主に建設業や運送業、林業、漁業等全12項目の事業に限られています。ここでは、建設業一人親方に該当する業種・職種について紹介します。
| ≪建設業種≫ | ≪具体的な職種≫ |
| 土木工事業 | 道路工事、橋梁工事、河川工事 |
| 建築工事業 | 元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 |
| 大工工事業 | 大工工事、型枠工事、造作工事 |
| 左官工事業 | 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 |
| とび・土工・コンクリート工事業 | とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリート・ブロック据付け工事、くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事、土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事、コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事、地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリングクラフト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事 |
| 石工事業 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 |
| 屋根工事業 | 屋根ふき工事 |
| 電気工事業 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事、(避雷針工事) |
| 管工事業 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事 |
| タイル・レンガ・ブロック工事業 | コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事 |
| 鋼構造物工事業 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事 |
| 鉄筋工事業 | 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事 |
| 舗装工事業 | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事 |
| しゅんせつ工事業 | しゅんせつ工事(河川、港湾等) |
| 板金工事業 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 |
| ガラス工事業 | ガラス加工取付け工事 |
| 塗装工事業 | 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 |
| 防水工事業 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング防水工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 |
| 内装仕上げ工事業 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 |
| 機械器具設置工事業 | プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル、地下道等の給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設場備工事 |
| 熱絶縁工事業 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事 |
| 電気通信工事業 | 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV 電波障害防除設備工事 |
| 造園工事業 | 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事 |
| さくい井工事業 | さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 |
| 建具工事業 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 |
| 水道施設工事業 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 |
| 消防施設工事業 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事 |
| 清掃施設工事業 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 |
| 解体工事業 | 工作物解体工事 |
ポピュラーな建設業の一人親方に関しては以下の記事でも詳しい説明をしています。
一人親方と個人事業主の違い
前述の通り、一人親方と個人事業主には従事できる業種が限定されているかされていないかという大きな違いがあります。
個人事業主の場合はとくに従事できない業種はないと言えますが、一人親方は特定の業種に限られますので、対象外の仕事を受注する場合は一人親方とは名乗らずに個人事業主として仕事をすることになります。
個人事業主の観点ではこちらの記事でも詳しい解説があります。
また、労災保険の加入資格の違いがあります。ここは特に重要となりますのでご一読ください。
労災保険の特別加入制度
特別加入制度は、通常は労働者が対象となる労災保険に、労働者ではない一人親方等も加入できる特別な制度です。これは、特定の職種や業種で働く一人親方が、仕事中のケガや病気、事故などに対して補償を受けられるように設けられたものです。
特別加入制度の対象となる職種、業種は主に建設業、運送業、漁業、林業、特定受託事業者(特定フリーランス事業)などで働く一人親方等(従業員を雇わず一人で事業を行う人)が対象となります。
※特定受託事業者として想定される職種・・・営業、講師、インストラクター、デザイン・コンテンツ制作、調査・研究・コンサルティング、翻訳・通訳、データ・文書入力 他
従って、上記に該当しない個人事業主は労災保険へ特別加入する資格はないということになります。
親方プラスでは、一人親方の労災保険を以下のようなサービスも付加し特別加入をサポートします。
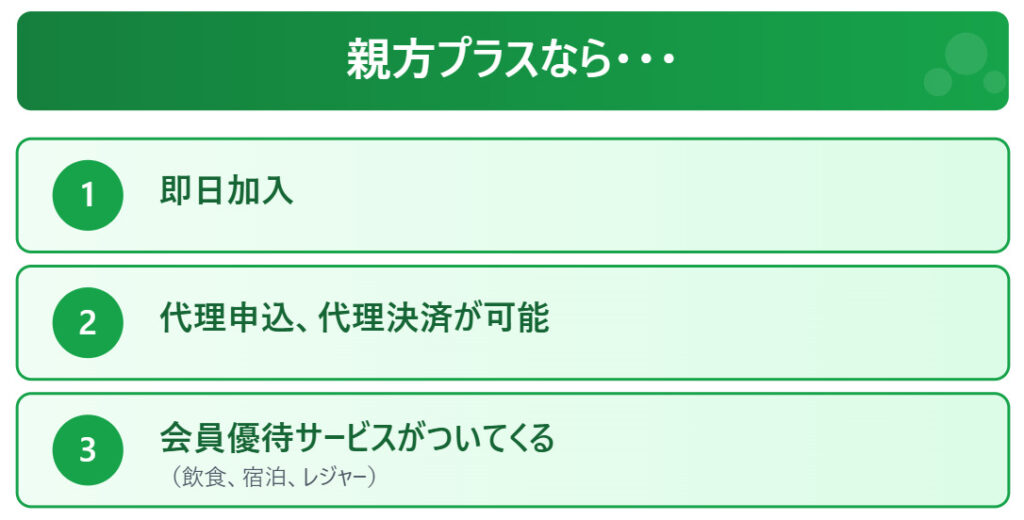
親方プラスなら・・・
- 即日加入
- 代理申込、代理決済が可能
- 会員優待サービスがついてくる(飲食、宿泊、レジャー)
一人親方労災保険の補償内容
一人親方の労災保険は、危険を伴う仕事をする場合も少なくありません。以下では主な補償内容について紹介しています。
- 療養補償(治療費)・・・業務中や通勤中に発生したケガや病気の治療費が全額補償されます。例えば、工事現場での作業中に転倒して骨折、高所作業中に落下して捻挫等、不慮の負傷等の場合が該当します。労災保険は自己負担なしで治療を受けることができます。労災指定病院での治療を受けるとスムーズな手続きが可能です。
- 休業補償(休業給付)・・・労災事故によるケガや病気で働くことができなくなった場合、休業4日目以降から給付基礎日額の80%が支給されます。医師の診断で労働不能の期間が続く限り、休業補償は受け取ることが可能です。ただし、医師の診断で回復と判断された場合や、仕事復帰が可能な場合は支給が終了となります。
給付基礎日額が10,000円の場合 → 1日あたり8,000円の休業補償が受けられる
- 障害補償・・・業務中の事故によって障害が残った場合、その障害の程度に応じて「障害補償年金」または「障害補償一時金」が支給されます。障害の程度は1級から14級まで細かく分類されており、重度の障害(1級〜7級)には年金が支給され、軽度の障害(8級〜14級)の場合は一時金が支払われます。例えば、現場作業中に鉄骨が落下し、大きなケガを負って片腕の機能を失った場合、該当する障害等級に応じた補償が適用されます。
1級(最重度の障害) → 障害補償年金が支給される
7級(中程度の障害) → 一部年金が支給される
14級(比較的軽度の障害) → 一時金として支給される
- 遺族補償・・・万が一、業務中の事故によって命を落とした場合、遺族に対して遺族補償給付や遺族年金が支給されます。この補償は遺族の生活を支えるためのもので、被災者が生前に得ていた収入に応じて給付額が決まります。遺族の人数や関係性によっても支給額が変動するため、詳細は個別に確認が必要です。
- 葬祭料・・・業務中の事故で死亡した場合、葬儀費用として一定額が支給されます。葬儀には多額の費用がかかるため、この補償があることで遺族の負担を軽減することができます。支給額は一定の基準に基づいて決定され、支給を受けるためには所定の手続きが必要になります。
- 介護補償・・・業務中の事故によって重度の障害が残り、常に介護が必要な状態になった場合、介護費用の補償を受けることができます。例えば、建設現場での重大な事故によって脊髄を損傷し、日常生活において介助が必要になった場合、この補償が適用されます。介護の必要度に応じて、定期的な支給が行われる場合もあります。
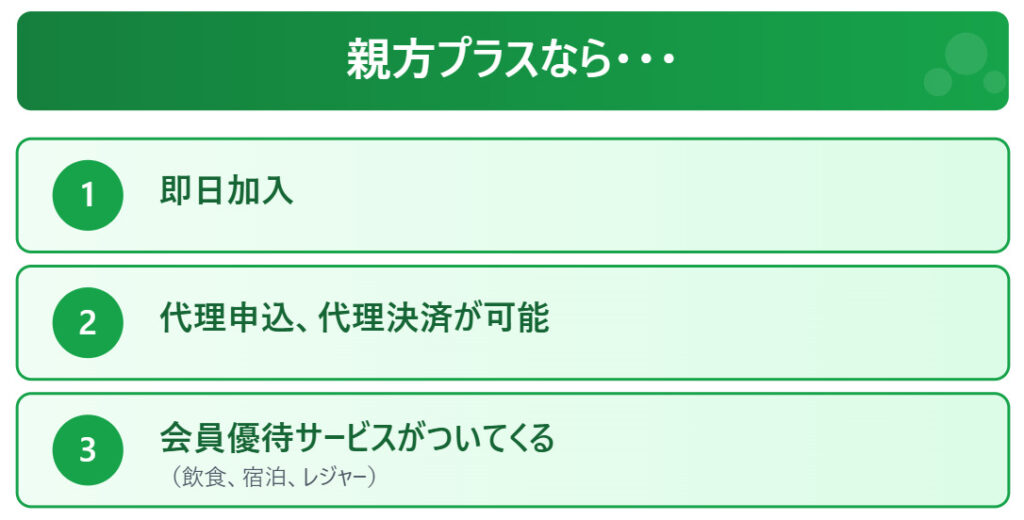
親方プラスなら・・・
- 即日加入
- 代理申込、代理決済が可能
- 会員優待サービスがついてくる(飲食、宿泊、レジャー)
一人親方と個人事業主の経費
そして一人親方や個人事業主として気になるのが経費の取扱いや税金についてではないでしょうか。
一人親方と個人事業主は、独立開業すると毎年必ず確定申告を行うことになります。その売上に対して差し引くことのできるものが必要経費といわれ、経費を差し引いた残りの売上に対して税金を計算し納めるという仕組みです。経費として算入できる項目が多ければ税金は安くなり、少なければ税金は多くなるということです。
経費にできる費用
一人親方が経費として算入できる代表的な費用は以下となります。
| 項目 | 具体例 | 備考 |
|---|---|---|
| 事務所関連費 | 家賃、水道光熱費、通信費(インターネット・電話代) | 自宅兼事務所の場合、按分が必要 |
| 車両費 | ガソリン代、高速料金、駐車場代、自動車保険、車検費用 | 私用との区別が必要 |
| 消耗品費 | 文房具、コピー用紙、インク、工具類 | 10万円未満のもの |
| 減価償却費 | パソコン、スマホ、工具、大型機械 | 10万円以上の場合、減価償却が必要 |
| 接待交際費 | 取引先との飲食費、手土産代 | 事業に関係するものに限る |
| 広告宣伝費 | ホームページ制作費、広告費、チラシ印刷代 | SNS広告も含む |
| 研修費 | セミナー参加費、書籍購入費 | スキルアップ目的 |
| 外注費 | 他の職人への外注費、デザイナーやライターへの依頼費 | 業務委託契約があると望ましい |
| 交通費 | 電車・バス代、タクシー代、出張時の宿泊費 | 業務に関連するもの |
| 会議費 | 打ち合わせ時のカフェ代 | 過度な高額利用は注意 |
| 租税公課 | 事業関連の税金(事業税など)、印紙代 | 所得税や住民税は対象外 |
| 福利厚生費 | 健康診断費、仕事用の作業着代 | 個人的な衣服は対象外 |
| 通信費 | 業務用スマホ代、インターネット回線 | 私用分は按分が必要 |
| 消耗品費 | 軍手、安全靴、工具など | 事業で使用するもの |
経費計上する際には、 領収書・請求書を保管 し、 事業に関係する支出であることを証明できるようにすることが重要です。
個人事業主は経費にできる科目は一人親方と変わりませんが、従業員を雇用している場合は上記の科目に加えて新年会・忘年会の費用、慶弔見舞金、健康診断費(全員受診要)、社員旅行などの福利厚生費も算入することができます。
経費にできない勘定科目
前述のように、一人親方が経費計上できないのが『福利厚生費』です。なぜ個人事業主だと経費にできて一人親方だとできないのでしょうか?
その理由は、一人親方の場合、あくまで一人で仕事をすることが前提なので、従業員を雇っていない一人親方は対象外となるからです。例えば、現場応援に来てくれる人やいつもチームとして動いてい仲間(子方等)は従業員(社員)ではありません。
また、個人事業主および一人親方は、株式会社、有限会社、合同会社などといった法人格を有さない個人事業(屋号)となります。そのため、民間の生命保険についてはどのような商品であっても経費算入することはできません。法人を契約者として被保険者を役員・従業員とする生命保険に関しては、商品によりその一部または全額を経費として取扱うことができます。
経費に関しては以下の記事でも詳しく解説しています。こちらも是非ご覧ください。
一人親方と個人事業主の個人事業税
一人親方と個人事業主で納める税金の種類で違いは特にありません。税金の種類は所得税・消費税・住民税・個人事業税の4つに分類されます。ここでは個人事業税についてその課税される条件について解説します。
個人事業税
個人事業税については、すべての一人親方および個人事業主に課せられるわけではありません。支払い対象者の条件は、大きく3つの条件からなります。
- 年間の事業所得が290万を超えている・・・個人事業税は、年間の売上から必要経費を控除した残りの事業所得が290万以下の場合、一律で事業主控除が受けられます。事業開始年度が12ヶ月に満たない場合は、月割りで控除を受けることができます。例えば、7月~12月の6ヵ月間事業を行った場合、145万円が控除される計算になります。
- 対象の事業であること・・・地方税制度に基づき、法廷業種として70業種が指定されています。それ以外の業種については個人事業税が課せられないことになります。
【東京都主税局HP引用】法廷業種と税率
- 個人事業主であること・・・個人事業主とは、法人でない「継続・反復で事業を行っている個人」のことで、開業届を提出している人を税法上「個人事業主」といいます。従業員を雇用していたとしても、法人を設立していなければ個人事業主に分類されます。一人親方も個人事業主です。
-
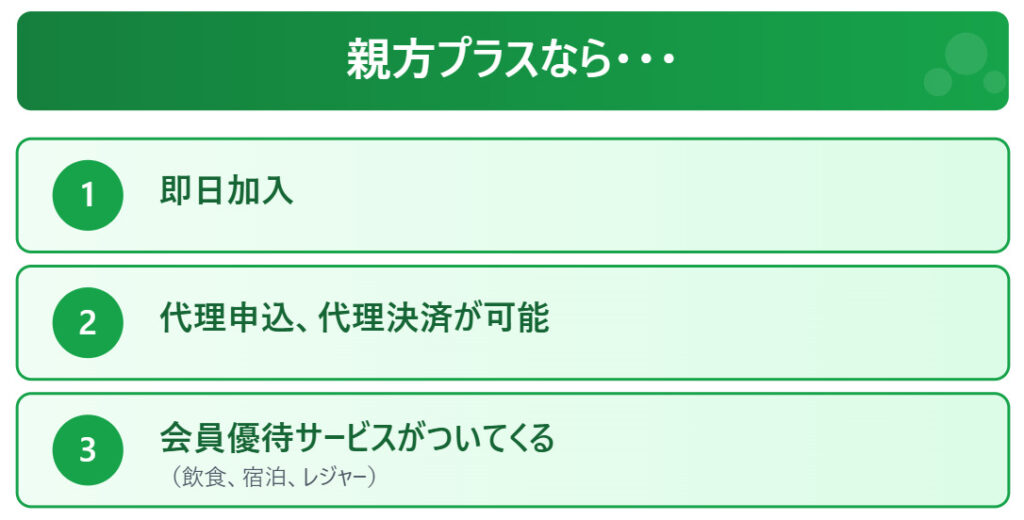
親方プラスなら・・・
- 即日加入
- 代理申込、代理決済が可能
- 会員優待サービスがついてくる(飲食、宿泊、レジャー)
一人親方と個人事業主のメリット・デメリット
一人親方として認められる条件と個人事業主のとの違いについて経費や税金の面などから違いについて解説してきました。結局、一人親方と個人事業主どちらがいいのか?それぞれのメリット・デメリットについてお伝えします。
【一人親方になる6つのメリット】
- 自由な働き方・・・自分のペースで仕事を進められ、勤務時間や仕事の内容を自由に決定できます。働きたい時間や休日を自分で調整できるため、ライフスタイルに合わせやすいです。
- 収入の自由度・・・受ける仕事の量や内容によって、収入が変動します。実力や仕事量に応じて収入が増える可能性があり、特にスキルや経験が豊富な場合、会社員以上の収入を得ることも可能です。
- 人間関係の自由度・・・自分一人で事業を行うため、社内の人間関係や上下関係に悩むことが少ないです。クライアントとの関係も対等な立場で調整することができ、自分の裁量で取引先を選ぶことができます。
- 経費の計上が可能・・・仕事に必要な経費(交通費、機材費、通信費など)を事業費として計上できるため、節税効果があります。個人事業主として節税策を工夫することで、手元に残る収入を増やすことが可能です。
- スキルアップの機会・・・事業運営の全てを一人で行うため、様々なスキル(営業、マーケティング、経理など)を身に付ける必要があります。この経験を通じて、広範な能力を養うことができ、今後の事業拡大や転職にも役立つ可能性があります。
- 事業の拡大が可能・・・成功すれば、一人親方から事業を拡大し、従業員を雇って法人化することも可能です。自身のビジョンや目標に合わせて、事業を自由に成長させることができます。
【一人親方になる6つのデメリット】
- 収入が不安定・・・仕事の量や取引先に依存するため、収入が安定しないことがよくあります。特に、仕事が少ない時期や顧客が減った時には収入が激減するリスクが高いです。
- 福利厚生がない・・・会社員のように社会保険、厚生年金、労災保険、健康保険などの福利厚生がありません。すべて自分で加入し、費用を負担する必要があります。また、病気やケガで働けない場合の保障も自己責任で準備する必要があります。
- 事業運営の全責任を負う・・・仕事の受注、納期の管理、経理、税務、顧客対応など、全ての業務を自分で行わなければなりません。特に事務作業や営業面での負担が大きく、経営全般に関する知識やスキルが必要です。
- 労働時間が長くなる可能性・・・自営業であるため、仕事が集中すると労働時間が長くなる傾向があります。また、案件をこなすために休日や夜間にも仕事をすることが必要になることがあり、ワークライフバランスが崩れやすいです。
- 資金調達や事業拡大の難しさ・・・一人親方の場合、資金調達や事業拡大が難しいことがあります。法人と比べて銀行や投資家からの信用度が低いため、融資を受けにくいことが多いです。また、大規模なプロジェクトに参加する際、信用力の不足が障害になることもあります。
- 税務や法務の複雑さ・・・自営業として税務や法務に関する知識が求められます。特に確定申告や消費税の申告など、税務手続きは複雑で、ミスをするとペナルティを受けるリスクもあります。
【個人事業主になる6つのメリット】
- 自由な働き方・・・自分自身で事業を運営するため、働く時間や場所、仕事の内容を自由に決めることができます。会社員と違って勤務時間に縛られず、ライフスタイルに合わせた働き方が可能です。
- 収入の増加ポテンシャル・・・自分の努力やスキルに応じて収入が変わるため、実力次第で高い収入を得ることができます。成功すれば、会社員としての収入を大幅に超えることもあります。
- 経費の計上が可能・・・事業に必要な経費(交通費、通信費、設備費、)を経費として計上することができます。これにより、税負担を軽減し、手元に残る利益を増やすことが可能です。
- 労働契約の束縛がない・・・企業に属していないため、特定の会社の規則や労働契約に縛られることなく、自由に取引先を選び、自分に合ったプロジェクトを遂行することが可能です。
- 副業や複数の仕事がしやすい・・・個人事業主として働いている場合、副業や複業がしやすくなります。1つの収入源に依存せず、複数の事業やプロジェクトを同時に進めることが可能です。※一人親方は特定の業種に限られます。
- 柔軟な引退・継続が可能・・・事業を途中でやめることや、事業内容を変えることが容易です。体力や状況に応じて事業を縮小しつつ続けることもできるため、ライフステージに合わせた柔軟な対応ができます。
【個人事業主になる6つのデメリット】
- 収入が不安定・・・仕事の受注量や景気の変動に大きく影響されるため、収入が安定しないことがよくあります。忙しい時期と仕事が少ない時期の差が大きく、一定の収入を確保することが難しい場合があります。
- 社会的保障が少ない・・・個人事業主には、会社員のような社会保険や厚生年金、労災保険などの福利厚生がありません。自分で国民健康保険や国民年金に加入しなければならず、万が一の病気やケガで働けなくなった際の保障が不足していることがあります。
- 税務処理や経理が複雑・・・確定申告や経費の管理、税金の計算など、経理作業をすべて自分で行う必要があります。特に青色申告をする場合は、複式簿記の知識が必要になるため、税務の知識や専門的なサポートを受けることが必要です。誤った申告をすると、追徴課税などのリスクもあります。
- 事業の全責任を負う・・・事業の成功や失敗、リスク管理を含めて、全ての責任を自分一人で負うことになります。顧客対応や契約の不備、クレーム処理などの対応も全て自分で行う必要があり、精神的な負担が大きいです。
- 融資や資金調達の困難さ・・・法人に比べて信用力が低いため、金融機関からの融資を受けることが難しい場合があります。また、事業を拡大する際に資金調達の選択肢が限られることが多く、大きな投資が必要な場合には困難に直面することがあります。
- 法的リスクへの対応・・・契約書の作成や取引の法的側面をすべて自分で管理する必要があり、法律に関する知識が不足している場合、トラブルや法的リスクに直面することがあります。特に、取引先とのトラブルや契約不履行などが発生した際の対応は個人事業主にとって大きな負担です。
一人親方の具体的な業種に関する詳細の記事もあります。それぞれの実態を知ることも重要です。
→ 電気工事士の一人親方
→ 塗装業の一人親方
→ 大工の一人親方
一人親方とは?個人事業主との違い まとめ
一人親方とは?そして一人親方と個人事業主の違いとそれぞれのメリット・デメリットについて解説してきました。
一人親方と個人事業主は、どちらも自分で事業を行う働き方ですが、いくつかの違いがありました。大きく5つの項目に分けてまとめてみます。
1.定義の違い
- 一人親方は、主に建設業、運送業、職人業など、特定の業種で使われる用語です。基本的に労働者を雇わず、自分一人で事業を行う形態を指します。特に建設業では、雇用されていない個人事業主として働く労働者を区別するために「一人親方」という言葉が使われます。
- 個人事業主は、特定の業種に限らず、自分一人で事業を運営する人のことを指します。様々な業種(IT、サービス、飲食、小売りなど)で個人事業主として働くことが可能で、労働者を雇っているかどうかは問いません。個人事業主は、雇用する場合も含め、自由な事業形態を選択できます。
2.対象となる業種の違い
- 一人親方の場合、特に建設業や運送業など、現場作業が主体の業種に多いです。また、職人や専門技術を持った人が、独立して一人で事業を行う場合によく使われます。
- 業種に制限がなく、クリエイター、コンサルタント、ITフリーランス、飲食店経営者、小売業者など、多種多様な業界で働けます。どの業界でも、自分で事業を立ち上げ、運営できる形態です。
3.特別加入労災保険の取扱い
- 一人親方は、建設業や運送業などでの労働災害に備えるため、「一人親方労災保険」という特別な制度に加入することが一般的です。この保険により、仕事中のケガや事故に対する補償を受けることができます。
- 個人事業主は、原則として労災保険へ特別加入する資格はありません。仕事中のケガや事故に対する補償については、必要に応じて民間の保険に加入してリスクに備えることも考えましょう。
4.従業員の有無
- 一人親方は、原則として従業員を雇わず、自分一人で事業を行います。ただし、家族が専従者として働くことなどはありますが、基本的には第三者の労働者を雇用しない形態です。
- 個人事業主は、従業員を雇うことができます。雇わない場合は一人で事業を行うことも可能ですが、事業が拡大した場合に従業員を増やしても構いません。
5.税務上の違いと経費科目
- 一人親方も税務上は個人事業主と同じ扱いを受け、確定申告が必要です。青色申告や白色申告などの選択肢があり、前述の経費科目の計上や控除を利用して節税することができます。
- 個人事業主も一人親方と同様に確定申告を行い、青色申告や白色申告の選択が可能です。事業規模や業種によって控除の内容は異なる場合がありますが、基本的な税務処理は共通しています。経費にできる科目は、従業員を雇用した場合に一人親方の科目に加え福利厚生費も経費の対象となります。
一人親方と個人事業主は、どちらも独立した働き方ですが使われる業界や事業規模、労災保険の加入資格の取扱いなどに違いがあります。すでに独立されている方、今後独立を考えている方ともに自分自身の将来ビジョンに合わせてどちらの選択が合っているのか。この記事を読んで参考にしていただけたら幸いです。
【こちらの記事もよく読まれています】
投稿者プロフィール

- 代表理事
-
いつもコラムをお読みいただきありがとうございます。
『建設業界を元気にしたい!』そんな思いで建設業に従事する方々が抱える問題点や悩み事に少しでもお役に立てれば幸いです。
【略歴】
・2011年 某外資系保険会社に入社
・2013年 労災保険特別加入団体の運営を開始
・2016年 大手生命保険会社100%出資代理店へ転身
・2024年 一人親方労災保険連合会【親方プラス】を設立 現在に至る
【趣味・特技】
キャンプ、つり、スキー、サッカー、ゴルフ…etc
最新の投稿
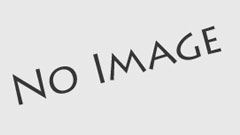 お知らせ2026年2月3日第2種特別加入労災保険の新年度更新時期となります
お知らせ2026年2月3日第2種特別加入労災保険の新年度更新時期となります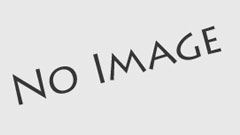 お知らせ2025年12月25日年末年始の休業日と新規ご加入についてのお知らせ
お知らせ2025年12月25日年末年始の休業日と新規ご加入についてのお知らせ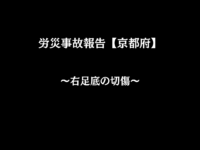 労災事例2025年9月25日【労災事故報告】令和7年8月7日 材料の運搬中に段差を踏み外し負傷したのも
労災事例2025年9月25日【労災事故報告】令和7年8月7日 材料の運搬中に段差を踏み外し負傷したのも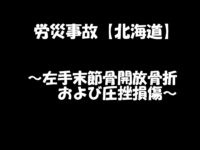 労災事例2025年8月25日【労災事故報告】令和7年8月11日 荷下ろし中にあおりに挟まれ末節骨開放骨折・圧挫損傷
労災事例2025年8月25日【労災事故報告】令和7年8月11日 荷下ろし中にあおりに挟まれ末節骨開放骨折・圧挫損傷

