大工の一人親方の平均年収は900万円!年収を上げるためにできること

大工の一人親方の平均年収は約900万円と言われています。会社員時代と比較すると、一人親方になって元請けとして工事を受注できるようになれば、年収は大幅に上昇します。
もちろん、これはあくまでも平均値です。実際には450万円程度の方もいれば、1,800万円以上稼ぐ方もいます。この記事では、大工の一人親方になる方法と、一人親方として年収を上げるための具体的な方法について詳しく解説します。
大工が一人親方として年収を稼ぐ心構え
大工の一人親方になるために最も重要なことは、仕事を依頼してくれる人脈を構築することです。まずは会社に所属して技能を習得しながら、人とのつながりを大切にしましょう。将来独立した際に仕事を依頼してくれるような関係を多く築いておくことが重要です。
通常、独立直後は元の所属会社から仕事をもらい、それを給料ではなく報酬として受け取ることが最初のステップとなります。最初の数ヶ月はこの方法で生活できるでしょう。
営業活動で受注できる体制を
しかし、元の会社も新たに従業員を雇用する可能性があり、また関係が悪化すれば仕事がなくなるリスクもあります。そのため、徐々に周囲の会社からも仕事を受注できる体制を整えましょう。
そのためには自分が独立したことを積極的に伝える必要があります。名刺を用意して現場の先輩方に挨拶し、機会があれば仕事をお願いする姿勢で営業活動を行いましょう。
これだけで必ずしも仕事がもらえるわけではありません。中には一生仕事をいただけない方もいるかもしれません。しかし、まずは頭を下げて「仕事を受けられる人」という認識を持ってもらうことが大切です。
そして、どうしても忙しくて仕事を依頼する人がいなくなった場合(そういう時期は必ずあります)に頼ってもらえるよう準備しておくことが重要です。
このようにして多くの人から仕事を受注できる状況になれば、晴れて一人親方として独立し、個人事業主として自分の城を持ち、事業を運営していくことができます。
一人親方については以下でも詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
大工が一人親方として独立するために
大工に限りませんが、一人親方として独立する際には、いくつか必要な手続きがあります。
1. 税務署への届出
まず税務署に足を運び、開業届と青色申告申請書を提出しましょう。これは事業開始の届出であると同時に、しっかりと記帳して事業を運営している証明となり、税金の節約にも役立ちます。いずれ必要な手続きなので、開業届と一緒に青色申告申請書も提出しておくと良いでしょう。
2. 市役所での手続き
次に市役所での保険関係の手続きが必要です。会社員時代は社会保険として健康保険に加入していましたが、一人親方になると国民健康保険に切り替わります。市役所や役場で手続きを行えば、その場で保険証を受け取ることができます。
会社を辞めた時点で社会保険は適用外となり、病院で保険診療が受けられなくなる可能性があるため、独立したらすぐに手続きを行いましょう。
3. 名刺を持っての挨拶回り
一人親方として最も困るのは仕事がなくなることです。現場にいる人たちは、あなたが一人親方なのか会社員なのかを見分けることができません。つまり、仕事を依頼していいのかどうかがわからない状態です。
これまで会社に所属していた人が独立しても、周囲の人が気づかないことが多いものです。職人を探している人がいても、あなたに声をかけられない状況になりがちです。
そのため、名刺を持って挨拶して回り、自分が一人親方となり仕事を受けられる状態であることを伝えましょう。「周りが気づいてくれるはず」と思うかもしれませんが、意外とあなたの変化に気づかないものです。
特に大切なのは、仕事がなくなってから挨拶回りをするのではなく、仕事が十分にある余裕のある状態で挨拶回りをすることです。余裕がある状態で仕事を受け、良い仕事をすることで将来の仕事につながっていきます。
「仕事の質が高ければ自然に仕事が集まる」と考える人もいますが、現実はそう単純ではありません。知り合いがいれば知り合いに仕事を回すことも多いため、将来困らないためにも名刺を持っての挨拶回りは必須です。
一人親方の年収に差が出る理由
一人親方の大工でも年収は様々です。同じ職種なのに年収に差がつく理由はどこにあるのでしょうか。
年収の違いは主に日当の違いに現れます。全ての人に平等に与えられるのは時間であり、同じ日当で同じ日数働けば同じ年収になります。1年は365日しかなく、働ける日数には上限があります。
つまり、年収が大きく違う理由は働いている日数の差ではなく、日当の高さにあります。では、なぜ日当に差が生じるのでしょうか。それは「日当が低い仕事を断れるかどうか」にあります。仕事を選べる立場にある人は日当の高い仕事を選び、結果として年収が高くなります。
仕事の質と評判の両方が重要
仕事が集まるためには、「仕事の技術の高さ」と「あなたの仕事の優秀さが周知されているか」の両方が重要です。例えば、非常に優秀な職人でも、引っ越したばかりで周囲に知り合いがいなければ、仕事は集まりません。その人の技術が知られていないからです。
逆に、地域で有名な職人でも、仕事が中途半端で遅刻が多ければ、余った誰にも頼めない仕事しか集まらず、年収は低くなるでしょう。
つまり、仕事の質とその評判の両方が重要です。両方を兼ね備えた時に仕事が集まり、日当の低い仕事を断れるようになり、結果として年収が上がっていきます。
一人親方の日当については以下でも詳しく解説しています。ご確認ください。
→ 一人親方の日当
労災保険も信頼を作るために重要
その人物が一人親方の労災保険に特別加入しているかどうかが、仕事を得る上で重要な場合もあります。
実際、一人親方労災保険の加入は任意ですが、大手ゼネコン系列の下請け仕事を受注する際はほぼ100%労災保険の特別加入が必要となります。
得られるチャンスをフイにしないよう、労災保険は必ず加入しましょう。当団体では以下のようなサービスを用意して、一人親方の皆さんを支援しています。
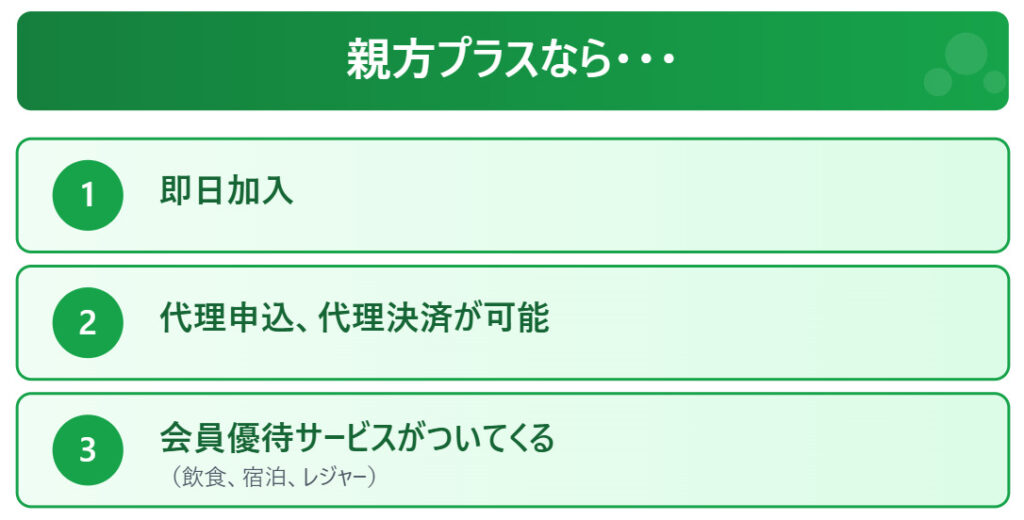
親方プラスなら・・・
- 即日加入
- 代理申込、代理決済が可能
- 会員優待サービスがついてくる(飲食、宿泊、レジャー)
【年収アップ】具体的な方法は2つ
年収アップのための具体的な方法は次の2つです:
- 名刺を持って仕事をいただく
- 期待値以上の仕事をする
一人親方の中には「依頼された仕事以上のことはしない」というポリシーの人もいますが、それでは「この人は仕事ができる」と思われることはなく、仕事は集まりません。金額以上の仕事をしてくれる職人がいれば、また依頼したくなるのは当然です。
最初は雑用も受けていたとしても、忙しいことが知られれば雑用は集まらなくなり、より高単価の仕事が舞い込むようになります。
つまり、年収を上げるには「名刺を持って挨拶回りをした上で、受けた仕事は金額以上の成果を返す」という地道な行動の繰り返しが効果的です。ぜひ参考にしてください。
大工の一人親方独立は計画的に
大工が一人親方になり、年収を上げる方法について解説してきました。大工としての技能はもちろんこと、挨拶回りや名刺配りなどの「営業活動」が年収差を拡げる大きな要因となります。
一人親方で高年収を狙うなら、会社員として人脈を拡げるなど下積みが重要です。実際に1000万円近い年収を得ている大工も存在するため、チャンスはそれなりに大きいといえるでしょう。
技能と営業で高収入を目指すなら、準備を整えて一人親方になりましょう。
投稿者プロフィール

- 代表理事
-
いつもコラムをお読みいただきありがとうございます。
『建設業界を元気にしたい!』そんな思いで建設業に従事する方々が抱える問題点や悩み事に少しでもお役に立てれば幸いです。
【略歴】
・2011年 某外資系保険会社に入社
・2013年 労災保険特別加入団体の運営を開始
・2016年 大手生命保険会社100%出資代理店へ転身
・2024年 一人親方労災保険連合会【親方プラス】を設立 現在に至る
【趣味・特技】
キャンプ、つり、スキー、サッカー、ゴルフ…etc
最新の投稿
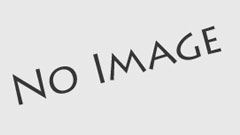 お知らせ2026年2月3日第2種特別加入労災保険の新年度更新時期となります
お知らせ2026年2月3日第2種特別加入労災保険の新年度更新時期となります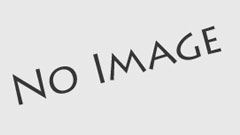 お知らせ2025年12月25日年末年始の休業日と新規ご加入についてのお知らせ
お知らせ2025年12月25日年末年始の休業日と新規ご加入についてのお知らせ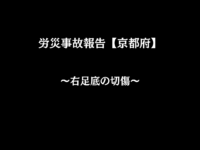 労災事例2025年9月25日【労災事故報告】令和7年8月7日 材料の運搬中に段差を踏み外し負傷したのも
労災事例2025年9月25日【労災事故報告】令和7年8月7日 材料の運搬中に段差を踏み外し負傷したのも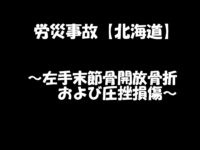 労災事例2025年8月25日【労災事故報告】令和7年8月11日 荷下ろし中にあおりに挟まれ末節骨開放骨折・圧挫損傷
労災事例2025年8月25日【労災事故報告】令和7年8月11日 荷下ろし中にあおりに挟まれ末節骨開放骨折・圧挫損傷

